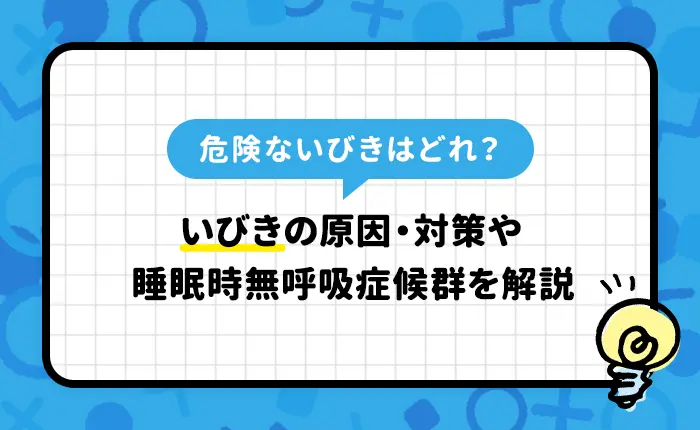睡眠中に発生するいびきは一般的なもので、男性の約57%、女性の約40%に見られ、年齢とともにいびきをする方が増えると言われています。
いびきは、自分で評価をすることが難しいものの、危険ないびきの場合は、早期発見・早期治療を行わなければ命に関わる恐れがあり、軽視できません。
本記事ではいびきの原因や対策について詳しく解説します。また、いびきの治療が必要とされる危険ないびきがどのようなものかや、具体的な治療についても解説するため、いびきに悩む方はぜひ参考にしてみてください。
いびきの原因といびきをかきやすい人の特徴
いびきは全ての人がかくものと思われる方もいるかもしれませんが、いびきはかきやすい人とそうでない人がいます。
また、いびきにはさまざまな原因があるため、いびきを改善したいと考えた場合、まずはいびきの原因を突き止めることが重要です。
いびきの原因とその特徴について解説します。
いびきの原因
いびきは何かしらの原因によって気道が狭まった結果として起こると考えられています。
この気道が狭まる原因は主に3つのタイプがあります。いびきの原因となる3つのタイプは次の通りです。
喉の筋肉が緩む
喉の筋肉が緩むことで気道がやや狭まるため、いびきがでやすくなります。このタイプは特に女性が多いと言われており、その理由が閉経です。
女性ホルモンは筋肉の緊張に関わるため、閉経によって女性ホルモンの分泌量が低下するといびきをする女性が増加します。そのため、40歳以上の女性でいびきがひどい方は、喉の筋肉が緩んだことが原因となるでしょう。
他にも、アルコール、疲労、睡眠薬の服用ものどの筋肉を緩ませるためいびきを誘発します。
骨格に問題がある
のどの周りに脂肪がついている、むくんでいるという場合には気道が脂肪などによって狭まるためいびきを起こしやすいです。また、顎が小さい方においては元々気道も狭いということが分かっているため、顎が小さい方や顎が後屈しているという骨格の方もいびきが発生します。
喉が腫れる
花粉症などのアレルギーや風邪をひくと、喉が腫れるため、気道が狭まり、いびきをかきやすくなります。ほかにも子どもに罹患者が多いアデノイドや扁桃腺肥大も炎症によって気道が狭まりいびきを誘発します。
口呼吸をしている
口呼吸の方は常に口が開いた状態で過ごしていることが多いですが、口が開いていると顎が下がり気道が狭まるため、いびきをかきやすくなります。
口呼吸になる原因はアレルギー系の病気で鼻詰まりが起こっていたり、口の周りの筋肉がもともと発達していなかったりするためと考えられています。
また、ストレスによっても口呼吸となることがあります。
いびきをかきやすい人の特徴
- 喫煙者
- 肥満
- 過度の飲酒
- ストレスが溜まっている
- 顎が小さい
- 閉経後の女性
- 口呼吸
- アレルギーがある
- 睡眠薬を服用している
- 仰向けで眠っている
いびきをかきやすい人には生活習慣が関係していることが伺えます。特に喫煙、飲酒、肥満はいびきだけでなく生活習慣病を発症させるリスクもあるため、早急の対策が必要と言えるでしょう。
また、顎の小ささや加齢など自分ではどうにも解決できないことが原因となっているケースもあることが分かります。
いびきの種類は3種類!なかには危険ないびきもある
いびきにもいくつかの種類があり、治療しなくてもいいタイプのいびきと、治療した方がいいタイプのものがあります。
いびきのなかには生命を脅かす危険ないびきもあるため、上述の原因に当てはまる方で、いびきを他人から指摘された経験のある方は、早期の解決が必要です。ここからは、いびきの種類を3つ解説します。
単純性いびき
単純性いびきとは病気の可能性がほぼないいびきのことをいいます。つまり、原因を取り除けばいびきが改善するものです。そのため、単純性いびきの方には治療の必要はありません。
上気道抵抗症候群
上気道抵抗症候群とは、いびきを習慣的にかいてはいるものの、無呼吸症候群や低呼吸などの基準を満たしていない状態のことを言います。自身のいびきによって夜間睡眠中に目が覚めることでいびきが止まります。
夜間に何度も目が覚めてしまうため、疲労感や不眠を訴える方が多い点が特徴です。そのため、単純性いびきの方でも翌朝に眠気や疲労感が残っている場合には上気道抵抗症候群へ分類されることがあります。
また、上気道抵抗症候群は前述したいびきをかきやすい人に当てはまらない方に発症しやすく、主に若い方や肥満ではない方、女性に多い傾向にあります。睡眠時無呼吸症候群にも単純性いびきにも当てはまらない新種のいびきとして1991年に発見されたいびきの種類です。
睡眠時無呼吸症候群
睡眠時無呼吸症候群とは睡眠中に呼吸が止まることで、後述するさまざまな合併症を引き起こす状態です。
呼吸が止まることで血液中の酸素濃度が下がり、目が覚め、入眠する、を繰り返すことで深い睡眠を得られなかった結果として日中に強い眠気が出現し、日常生活にも影響を引き起こします。
日本呼吸器学会によると、睡眠時無呼吸症候群の診断基準は、10秒以上息が止まる状態が平均して1時間に5回以上見られた場合には確定となり、15回未満で軽症、30回未満で中等症、30回以上で重症と診断されます。
成人男性の約3~7%、女性の約2~5%にみられ、男性では40~50代、女性では閉経後の方に発症者が多いです。
また、いびきだけでなく、起床時の眠気や頭痛、日中の眠気を強く感じるため、日常生活や社会生活に影響しやすくなります。
睡眠時無呼吸症候群は早期治療・対策が大切
睡眠時無呼吸症候群はさまざまな病気の発症リスクにもなるため放置せずに早期発見と早期治療、そして対策をしてくことが重要です。
とはいえ、忙しくて病院に行けない、今元気だから大丈夫と思う方もいるかもしれません。睡眠時無呼吸症候群を放置するリスクについて詳しく解説します。
睡眠時無呼吸症候群を放置することのリスク
睡眠時無呼吸症候群を放置することはさまざまなリスクにつながりますが、特に怖いのが合併症の発症です。睡眠時無呼吸症候群は生活習慣病と深く関連することが分かっており、高血圧、心臓病、脳卒中、糖尿病などを合併する可能性が高まります。
日中に強い眠気を感じると酸素濃度が低下するため、心臓の働きが強まり、高血圧や動脈硬化など心臓の疾患を発症する可能性が高くなります。
実際に睡眠時無呼吸症候群の成人が高血圧や心臓病、脳卒中を発症するリスクは健常者の約3~4倍で、重症例においてはリスクが5倍に高まるのです。また、ストレスによって糖代謝が乱れて糖尿病を発症させるリスクも高まります。
もう1つ睡眠時無呼吸症候群を放置することで危惧されるのが社会生活への影響です。日中に強い眠気が出ることから、日常生活や仕事へ多大なる影響を及ぼします。
居眠り運転での事故の増加
特に影響が懸念されているのが車の運転です。睡眠時無呼吸症候群の方の交通事故発症割合は、健常の方の2.5~7倍と報告されています。そのため、現在の道路交通法では睡眠時無呼吸症候群の事実を隠して運転免許を取得した場合に法律で罰せられます。
参考文献:成田赤十字病院
つまり、睡眠時無呼吸症候群の方は治療をして改善しないと今後車の運転ができなくなる可能性があるのです。
さらに強い眠気によって作業効率が低下するため仕事で思わぬミスをしたり、労働災害に見舞われたりするリスクもあり、早期の改善が必要です。
こんな症状は睡眠時無呼吸症候群のサインかも!
- ほかの部屋にまで聞こえる大きく不規則ないびき
- 呼吸の途絶え
- 息苦しそうな音
- 寝起きがスッキリしない、日中の眠気を伴ういびき
- 夜間の覚醒回数が多いいびき
- 1時間に5回以上呼吸が止まっていると周囲に指摘された
睡眠時無呼吸症候群は、気道の閉塞によって十分に酸素が流入してこないことから一生懸命呼吸をしようとします。その結果としていびきの音が大きくなります。
また、呼吸が夜間複数回止まることから、寝起きがすっきりせず、日中に強い眠気を伴うようになるのです。
普段一緒に寝ているパートナーから睡眠中に息が止まっていることを複数回指摘されている方は、睡眠時無呼吸症候群を疑い一度病院を受診することがおすすめです。
いびきを改善させるための対策法
いびきは健康にも日常生活にもさまざまな影響を与えるため、対策を講じたいと考える方もいるかもしれません。
睡眠時無呼吸症候群のように病気が絡んでいる場合には治療を受けることが適切ですが、病気が絡んでいない場合には日常生活の中で対策することで改善できます。
いびきを改善させるための対策について解説します。
①:生活習慣の改善
いびきは生活習慣が強く関係しているため、生活習慣の改善を意識しましょう。特に重要視したいのが肥満の改善です。首周りの脂肪が無くなることで気道が広くなりいびきを改善できる可能性が高まります。
肥満改善に重要なのは、食生活の改善と適度な運動習慣、そして嗜好品の見直しです。以下で詳しく解説します。
食生活の見直し
食事面では1日3食バランスよく食べることを心がけ、特に野菜や海藻、キノコ類の摂取を心がけましょう。揚げ物やスナック菓子、洋菓子などの脂肪分の摂取は控えることも必要です。
炭水化物も食べ過ぎると脂肪へとつながるので、控えめにしましょう。また、間食もできるだけ控え、ゆっくりとよく噛んで食べることも心がけてください。甘い飲み物も控え、水やお茶のみとすると良いです。
適度な運動
食生活と併せて行いたいのが適度な運動習慣です。脂肪を燃焼させるためには有酸素運動がおすすめです。とはいえ、肥満の方は自身の体が重いため、縄跳びなど負荷のかかる運動をいきなり始めるとケガをするリスクもあります。
そのため、ジョギングやウォーキングなどの体に負担なくできる運動から始めてみましょう。
嗜好品の見直し
アルコールやたばこといった嗜好品はいびきの悪化につながるため見直しましょう。
特にストレス解消や就寝前に寝酒と称してアルコールを嗜む方もいるかもしれません。しかし、アルコールは睡眠の質を低下させるうえに、糖質を含んでいるため肥満にもつながるため、控えましょう。
また、たばこも避けるべき嗜好品です。たばこに含まれるニコチンは睡眠の質に影響します。それだけでなく、たばこの煙が喉に炎症を起こして気道を狭くしたり、血液中の酸素濃度が下がり呼吸が苦しくなるため夜間の覚醒へとつながったりします。そのため、できれば禁煙を心がけましょう。
②:寝る体勢や寝具を見直す
仰向けで寝ると重力によって舌の付け根が喉元まで落ち込み、気道が狭まるためいびきを発症させます。そのため、寝る時には横向きかうつ伏せで眠りましょう。ただし、うつ伏せは顔を横に向けることで首を傷める可能性があるので横向きがベストです。
しかし、横向きで眠ることで改善効果が見込めるのは軽症の場合です。重症の場合は寝る位置を変えても大きな改善効果は見込めません。また、いびき対策として自身に合った枕を使用したり、マットレスを変えたりすることもおすすめです。
③:いびき対策グッズを使用する
いびき対策グッズを使うことでいびきの改善や軽減へとつながる可能性もあります。いびき対策グッズには現在さまざまなものがありますが、特によく使われるのが鼻腔拡張テープ、マウスピースです。
鼻腔拡張テープ
鼻腔拡張テープとは、テープの中央に弾力のあるプラスチックが付着されているもので、鼻前庭の外側壁を引き上げることにより、鼻弁部の断面積を増加させた結果、鼻腔の通気を増加させる効果を期待します。
痛みなどもない上に簡単にできることからいびき対策として手軽に取り入れやすい点が特徴です。しかし、テープの形は一定であるものの鼻の形には個人差があるため、効果が得られないという方もいます。
マウスピース
いびき対策用のマウスピースはあおむけに寝たときに舌が喉の奥に垂れ込むことを防ぐ目的があります。
下顎と舌を前方に移動させて固定するものと、舌を吸引して前の方で固定するものの2つがありますが、前者の方が違和感なく使えることが多いため、前者を使う方が多い傾向にあります。
市販もありますがマウスピースは歯並びなどにも影響することから歯科医院で十分な知識と経験のある歯科医が作成することが勧められているものです。
④:病院で、いびき治療を受ける
もしかしたら睡眠時無呼吸症候群かもしれない…と思っておられる方には、一度医療機関を受診されることをおすすめします。
いびきの治療は耳鼻咽喉科や呼吸器内科でもできますが、いびき外来、睡眠呼吸センターなど専門医もおられます。
いびきの治療は中等度以上の場合、経鼻的持続陽圧呼吸療法(CPAP)といって寝る時にマスクを装着し、そこから送り込む空気の圧力で気道が閉塞しないようにします。軽度の場合はレーザー治療が可能なこともありますが、医師の診断で治療法が決定します。
まとめ
- 日中の眠気や疲労感が軽減
- 睡眠時無呼吸症候群やそれに伴う合併症のリスク軽減
- 家族やパートナーの睡眠を妨げない
- 友達との旅行も安心して楽しめる
寝ている間に無呼吸になってしまう危険ないびきは、医療機関での治療が当然必要ですが、単純性いびきも治療をすれば多くのメリットを得られます。女性の方であれば、本来治療する必要がないタイプのいびきでも、治療をしたい方は多いはず。
睡眠時無呼吸症候群の検査や治療は、保険適用となることも多いですので、まずは一度医療機関に相談してみてはいかがでしょうか。
兵庫県医科大学病院|睡眠時無呼吸症候群
成田赤十字病院|放置すると危ない病気 睡眠時無呼吸症候群
日本医師会|病気のシグナルかも?いびきにご注意